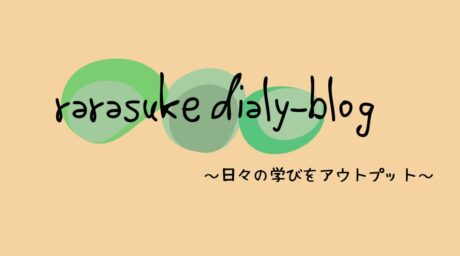この記事では小児期のこころと言葉の発達について生後~12歳以降の年代別に分けて
分かりやすく解説いくものになります。
ボク自身も小児リハビリテーションについて勉強中です。
一緒に理解を深めていきましょう!
この記事で分かること
・子どものこころと言葉の発達の特徴
・生後~2歳(感覚運動期)の特徴
・2~7歳(前操作期)の特徴
・6~11歳(具体的操作期)の特徴
・12歳以降(形式的操作期)の特徴
※この記事では参考文から、Piajetの認知発達段階説をもとに解説します。
子どものこころと言葉の発達の特徴
子どものこころの発達は、言葉の発達と親などの身近な存在との関わりにより
生後から徐々に他者とのコミュニケーションの手段を変化させていきます。
産まれて間もなくは泣き声を発したり、新生児微笑のように表情の変化がみられます。
親はこの泣き声や微笑に対して、抱きかかえることや話かけることで関わりをもちます。
生後2~3ヶ月後から社会的微笑がみられ、周囲からの刺激を受けての反応がみられるようになります。
4ヶ月頃から「あー」「うー」といった喃語を話すようになり
6ヶ月頃から「まんまんまん」「なんなんなん」といった反復喃語が聞かれます。
10ヶ月頃には興味のあるものを指さし「あー」というなど、コミュニケーションの兆候がみられるようになります。
1歳頃から「ママ」「パパ」のような1語文
1歳6ヶ月頃から「ママ、だっこ」のような2語文を話すようになります。
これ以降は爆発的に語彙が増えるようになり
小学校にあがる頃には
頭では6,000~8,000語の単語を理解し、2,500語前後の単語を発するようになると言われています。
この変化の中では
語彙の増加という“量的変化”と2語文話せるというような“質的変化”
さらに、「増える・できるようになる」といった上昇的変化と
「減った・できなくなった」といった下降的変化がみられます。
減ることやできなくなることは必ずしも悪いことではありません。
不必要な能力が減ることで、より効率的な情報処理を行えるようになる変化もみられるからです。
このように、子どものこころと言葉の発達は
泣く・笑うといった表情的なコミュニケーションツールから
話すという言語的なコミュニケーションツールに変化していく特徴がみられます。
言葉は保護者や養育者の発した言葉を音声刺激としてとらえて学習されます。
それと同時に、新生児の段階から子ども自らが発した、泣き声や笑顔、発声に対する
保護者たちのリアクションを受け取ることで社会的な関わり方を学習すると言われています。
つまり、子どものこころと言葉の発達には、特に保護者や養育者といった身近な存在との関わりが重要と言えます。
生後~2歳:感覚運動期の特徴

生後~2歳頃までは、感覚や運動を通じて自分と他者や環境との関わり方を覚えていくことが特徴です。
これは五感を中心とした感覚や身体運動によって
周囲からの刺激を受けて、自分と周囲の環境との相互関係を構築しつつ
認知機能を発達させる時期です。
例えば、「これはボールだよ」と働きかけるよりも
「赤いボールだね」「つるつるしているよ、触ってごらん」といったように
複数の五感に働きかけるとよいとされています。
2~7歳:前操作期の特徴

2~7歳頃は、自我が芽生え自己主張できますが、他者の立場になって考えることはまだ難しいという特徴があります。・・・こんなの大人でも難しい。
この時期にはイメージで物事が理解できるようになります。
しかし、この段階でのイメージは十分に理論的ではないため
夢と現実が混同したり、人形や機械にも心や感情があると考えてしまうことがあります。
また、他者視点で考えることが十分に備わってないため
自分が経験したことや感じたことは相手も理解していると誤認してしまうことがあります。
自我が芽生えて、自分の要求を訴えるようになるため
いわゆる「イヤイヤ期」や「第一次反抗期」と言われる時期にあたります。
関わりかたとしては、本人の訴えに耳を傾けることや
「あなたはそう思うんだね、でも他の人はどうかな?」というような
他者視点を育むような声かけが重要と言えます。
6~11歳:具体的操作期の特徴

6~11歳頃は、具体的な事柄は理解が可能だが、抽象的な事柄の理解には困難さを抱く特徴があります。
例えば、算数の1+1を「リンゴが1つとミカンが1つ...」のように具体的な物で考えたり、指折り数えたりすることで理解します。
一方で、怒りや不安、嬉しいなどの言葉としては感情を理解していても
自分の今の状態を言語化することは難しく
「なんか嫌だった」と曖昧な理由で拒絶したり、ケンカしたりしてしまう場合があります。
12歳以降:形式的操作期の特徴
12歳以降は、およそ成人と同様の思考が可能になる水準まで認知機能が発達している時期です。
そのため、仮定の話や例え話などを使って他者とのコミュニケーションをとれるようになり
感情やイメージを他者と共有できるようなり、互いに理解しあうことも可能になります。
その一方で、他者と自分を比較することで、悩みや葛藤が生じて第二次反抗期に入る時期になります。
まとめ
子どものこころと言葉の発達には「量的変化」「質的変化」が含まれ
それらの「上昇的変化」と「下降的変化」がみられる。
「下降的変化」は情報処理や他者理解の効率化を図るという変化も含まれる。
生後~2歳は五感を通して、自分と自分以外のものとに気づく時期
2~7歳は自我が芽生え自己主張ができるようになる時期
6~11歳は自分と他者との関わり方が形成されていく時期
12歳以降は社会的なつながりの中で相互理解を求め、コミュニケーション能力が進展していくようになります。
コミュニケーションツールが年代により変化することには
身近な存在との関わり方が重要になります。
語彙や理解の成熟には欠かせない要因と言えると思います。
リハビリスタッフとしては、発達障害や知的障害のある子どもに対して
早期援助・対応することが重要視されています。
その子1人ひとりに合わせて、相互理解が深まるような
成長と発達を促せる支援ができることも重要ですね。
最後まで読んでいただきありがとうございました!