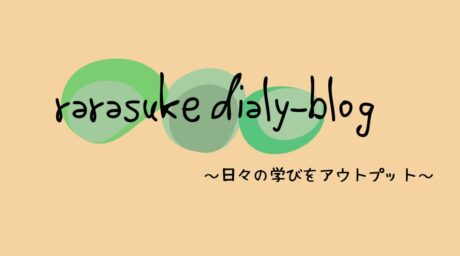今回は子どもの呼吸器の発達と医療的ケアやリスク管理について
理学療法士の視点から解説します。
ボクも小児リハビリについて勉強中です
小児リハビリは子どもや家族を中心に考えて、進めていくものだと思います。
相手の気持ちの変化が分かるように日々勉強です!
一緒に理解を深めましょう!
この記事を読んで分かること
・子どもの呼吸器の発達と解剖生理学的な特徴
・呼吸に関する医療的ケアの概要
・生活期を想定したリスク管理の概要
・呼吸ケアや呼吸機能の発達と成長に必要なポイント
※この記事は論文や参考書をもとに筆者の解釈をまとめたものです。
子どもの呼吸器の発達と解剖生理学的な特徴
1.子どもの呼吸器の解剖生理学的な特徴
~新生児の呼吸器の解剖生理学的特徴~
- 口腔容積が小さい
- 舌が大きい
- 軟口蓋と喉頭蓋が近い
- 気道は細い
- 肺は硬いが、胸郭は柔らかい
- 生理的屈曲姿勢により鼻呼吸がしやすい
まず、新生児の解剖学的特徴として、口腔容積が小さく、舌が大きいです。
これは口の中は狭いのに舌ベロが大きいため、呼吸はしにくい環境です。
それに加えて、軟口蓋と喉頭蓋の間が近いため、口の中の奥行も小さいことになります。
とても口呼吸がしやすい環境ではありません。
この対応策として、赤ちゃんは生理的屈曲姿勢をとります。
これは体を丸めるようにすることで、鼻呼吸をしやすいような姿勢になります。
そして、鼻呼吸ができることは哺乳が容易になります。
2.子どもの呼吸器の発達
出生時の肺は未熟であり、8歳頃まで成長すると成人と同数の肺胞数まで成熟します。
新生児のときは、口の中が小さく、気道も細いため
生理的屈曲姿勢を用いて鼻呼吸を行い
哺乳や随意的な嚥下能力を獲得すると言われています。
それにともない、頸部の筋群の発達し、いわゆる「首がすわる」状態になります。
首が座ってきたら、腹這いの練習をされると良いとされています。
これは腹這いの状態から頭を起こして顔を挙げることで
気道が広がることで上気道の確保がされるためです。
また、ハイハイや座位保持をすることで胸郭が広がりやすくなり
横隔膜がよく働くようになるため呼吸器の機能が向上されると言われています。
以上が、一般的な子どもの呼吸器の特徴と成長過程の説明になります。
子どもの呼吸に関する代表的な医療的ケア
呼吸に関する代表的な医療的ケアの種類
- 気管切開の管理
- 在宅人工呼吸療法
- 在宅酸素療法
- 排痰補助装置の使用
- 吸入
- 吸引
これらの医療的ケアはなんでも導入すれば良いという訳ではありません。
対象者がどのような疾患をもっていて、どのような状態なのかで導入すべき手段が変わります。
例えば、上気道が狭くなっているため呼吸が困難な場合は気管切開を導入したり
一方で、肺でのガス交換や換気が障害されている場合は在宅人工呼吸療法や在宅酸素療法などを選択したり
そのときの状態や医師の処方などによって最適な手段が選ばれます。
医療ケアに対するリスク管理
1.気管切開のリスク管理
気管切開には単純気管切開と喉頭気管分離術がある。
・単純気管切開:気管孔(人工呼吸器の管を挿入する孔)を塞いでも呼吸可能
・喉頭気管分離術:気管孔を塞ぐと窒息する
気管切開の場合はどちらも、計画外の抜管に注意する。
また、気管支に傷ができることで発生する肉芽を予防するために
頸部の運動と管の位置に配慮する必要があります。
さらに、気管の前には動脈があるため、頸部が過度に伸展すると動脈が傷つき
大出血を起こすリスクがあります。
気管切開の導入にはご家族様やご本人様の意向と医師に対する十分な相談が必要になります。
2.医療機器などに対するリスク
医療機器の操作に関して十分に理解する必要があります。
誤操作による身体的不利益や想定外の抜管などを起こさないための配慮が必要です
3.感染予防のリスク
肺炎や感染症を起こさないように、在宅でケアにあたる家族にも
清潔に保つことや機器を清潔に保つことなどの十分な理解を促す必要があります。
一般的な衛生管理の理解と継続できているかの確認をする必要性があります。
4.全身状態のリスク管理
普段の状態と比べて違うところがないか気づけるようにする必要があります。
顔色の変化や呼吸状態などの主観的な様子や
体温や血圧、酸素化の値など客観的な数値などを記録して
把握できるようにしているとよいと言われています。
5.骨折のリスク管理
障害により運動による刺激が少なかったり、病的に骨密度が低下している場合
体位変換や呼吸介助などをしたときに骨折してしまうケースがあります。
医療機関から骨密度や骨折しやすいと言われたことのある場合は十分に注意して介助する必要があります。
6.気管支攣縮のリスク
攣縮とは、けい攣のことです。
気管支を覆っている筋肉がけいれん攣することで呼吸困難感や
喘息のときのような「ひゅーひゅー」と音のする呼吸が起こります。
特に、気道が過敏になっているときには注意が必要です。
呼吸ケアや呼吸機能の発達に必要なポイント
呼吸ケアを必要とする子どもは、入院期間が長いことや、入退院を繰り返すため、
親や養育者との愛着形成がしにくい場合がある。という問題があります。
理学療法士として、呼吸理学療法の視点からアプローチを行い
呼吸が楽になる ⇒ 運動が楽になる ⇒ 様々な体験から愛着形成や運動発達が展開される
このような良いサイクルが作れるように進める必要があります。
呼吸が苦しいとは、生命の危機でもあります。
そのような状態では、本人も家族もなかなか外出や運動に気持ちが向かないのは
想像に難しくありませんよね。
リハビリスタッフとして、ご本人様やご家族様の生活が豊かになるように関わることは
リハビリテーションの本質に重要なポイントになります。
まとめ
- 解剖生理学的に新生児は呼吸器が未熟なため、呼吸に不利になりやすい
- 一般的には頭頚部の筋群や粗大運動の発達にともない気道や肺などの呼吸器も発達する
- 疾患や障害がある場合、生命の安全を確保するため、外出など社会的な活動が難しいケースがある
- リハビリテーションを通じて、『呼吸が楽⇒運動が楽⇒生活が豊かになる』良いサイクルを目指すことが重要
一般的な知識や推奨される関わり方をまとめました。
しかし、今回紹介した知識がぴったり当てはまるケースは少ないと思います。
その人によって重症度や身体能力は違うため
リハビリスタッフとして評価や実践を通して
その人に最適な手段や方法をみつけること
そして悩み続けることが大切なんじゃないかと
個人的に思います。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました!