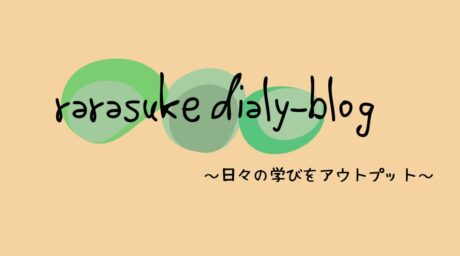今回はエネルギー代謝を考えるのに必要な3大栄養素の特徴についてまとめます。
ダイエット記事でも糖質制限や脂質制限といった言葉が目立つ昨今ですが
糖質や脂質は私たちの敵なのでしょうか?
生命維持活動に必要な栄養素だとボクは考えています。
また、臨床現場では、心疾患や糖尿病患者様の生活習慣の改善について指導するときや
ダイエット指導をするときに関わるエネルギー代謝についての話をよくします。
生活習慣や体型改善については基本的には『食事』と『運動』が重要です。
適切な食事量や運動量は個人差があります。
その個人差を評価・判断するための要因のひとつとして
エネルギー代謝について考える必要があります。
このときのエネルギーを作るのが3大栄養素になります。
これらがどのような役割や特徴があるのか
漠然と知っているより、特徴を理解したほうがエネルギー代謝についての理解も深まります。
また、ダイエットなどで過剰な制限をして不健康におちいるリスクも少なくなると思います。
ダイエットや糖質制限や脂質制限をすることが悪いのではなく
中途半端な理解で過剰にやりすぎること(過剰摂取も過剰制限も...)が悪いことだと思います。
この記事は理学療法士はもちろん、ダイエッターの方にも分かるようにまとめています。
ぜひ最後まで読んで、一緒に理解を深めていきましょう!
この記事を読んで分かること
- 3大栄養素とは何か
- 3大栄養素の特徴と役割
- エネルギー代謝の基礎知識
3大栄養素の役割と特徴
人間が生命維持活動を行うためには、食事からエネルギーを産生する必要があります。
このエネルギー産生・代謝を営むうえで重要な3大栄養素があります。
それは『糖質』『脂質』『たんぱく質』の3つです。
この3つの特徴や役割、エネルギー産生量などをそれぞれ解説、まとめていきます。
糖質
特徴
- 主要なエネルギー源
- 最終的にはブドウ糖に分解され吸収される
- 吸収されたブドウ糖はグリコーゲンとして筋や肝臓に貯蔵
- 余ったグリコーゲンは脂肪として蓄えられる
- エネルギー代謝のとき完全に酸化・燃焼される
糖質は水素、炭素、酸素からなる栄養素です。
単糖類、少糖類、多糖類の3つに分類されます。
多糖類のでんぷんやグリコーゲンがあります。
糖質は食物の半分以上を占めており、主要なエネルギー源となります。
この多糖類は水に不溶性の性質をもちますが
自然のでんぷんは顆粒状であり、調理によって消化が容易になるとされています。
要するに加工物とかは消化に良くないよね。お米やお芋のでんぷんは料理すれば消化しやすくて
内臓にも優しいよね。といった感じです。
多糖類は消化により、最終的にブドウ糖として吸収されます。
このブドウ糖は各細胞で酸化しエネルギー放出をするとともに
グリコーゲンとして筋肉や肝臓に予備エネルギーとして貯蓄されます。
また、余分なものは脂質として合成されます。
このとき、糖質がエネルギー源となるか、グリコーゲンとなるかは血中濃度に関係すると言われています。
脂質
特徴
- 主要なエネルギー源
- 皮下脂肪組織となる
- 脂溶性ビタミン(D,E,K,A)を運ぶ
- 消化と胃酸分泌を遅らせる
- コレステロールはホルモン、酵素、細胞膜の材料
- エネルギー代謝では完全に酸化・燃焼される
有機溶媒(エーテルやクロロホルムなど)に溶けて、水には溶けないものを脂質と呼びます。
典型的な脂質は炭素、水素、酸素からなります。
栄養素として取り込まれた脂質には脂肪酸やアルコールが含まれます。
その他にも、アミノ酸や蛋白、糖、リン酸なども含みます。
また、ステロイドや脂溶性ビタミンなど誘導脂質と呼ばれるものも含まれます。
脂質の主な役割はエネルギー源となることや、貯蓄エネルギーとして脂肪組織になることです。
また、脂溶性ビタミンの運搬や細胞膜や酵素の材料となることで
身体組織の維持や形成に関わります。
一方で、胃酸分泌や消化を遅らせる作用もあるため過度な摂取は内臓の負担を増大させます。
また、小児や高齢者ではもともとの内臓機能が未発達だったり、低下していたりするため
脂肪の消化は遅くなると言われています。
たんぱく質
特徴
- 構成要素に窒素を含む
- アミノ酸として吸収される
- 新しい組織を作るときや古い組織を修復するときに利用される
- 糖質や脂質が不足したときのエネルギー源となる
- 水分バランスを保つ
- 抗体産生に利用される
- 酵素やホルモンの材料になる
- エネルギー代謝では完全に酸化・燃焼されない
たんぱく質は基本的に身体組織や酵素、ホルモンなどの材料としての役割があります。
エネルギー産生では積極的には使用されないと言われています。
そのため、食物エネルギーからエネルギー代謝を行うとき
糖質や脂質は完全に酸化・燃焼されますが
たんぱく質は完全には酸化・燃焼されません。
また、たんぱく質に含まれる窒素は尿素やアンモニアなどの窒素化合物として尿として排泄されます。
そのため、腎機能の低下した疾患の方にはたんぱく質を制限した食事管理などが行われます。
たんぱく質は消化され最終的にはアミノ酸となります。
必須アミノ酸と呼ばれる9種類のアミノ酸は食事でしか取り入れることができず
人体内で作ることができません。
逆に、非必須アミノ酸に分類されるものは、必須アミノ酸をもとに
体内で作ることができるアミノ酸です。
生命維持のために食事が重要な理由のひとつになります。
エネルギー代謝の基礎知識
筋収縮には摂取した栄養素からATP(アデノシン三リン酸)を利用して熱産生を伴います。
この熱産生量をからエネルギー産生に代謝された栄養素がわかります。
このエネルギー量の単位はカロリー(cal)と呼びます。
1calは1気圧のもとで水を14.5℃から15.5℃に上昇させるのに必要な熱量です。
このエネルギー代謝の測定にはいくつかの方法があります。
熱量計で測定する方法
物理的燃焼値:食物中に含まれるエネルギー量の測定
糖質:脂質:たんぱく質=4.10:9.45:5.65 kcal
生理的燃焼値:生体内での食物エネルギー量の測定。物理的燃焼値より低くなる
糖質:脂質:たんぱく質=4:9:4 kcal
人体のエネルギー代謝の測定は酸素消費量で計測する。
このときに、一定時間で消費した酸素量と排出した炭酸ガスの量から
呼吸商を算出します。
呼吸商は
糖質:脂質:タンパク質=1.0:0.7:0.8
となります。
このように3大栄養素からのカロリー算出には様々な方法がありますが
摂取、消化、吸収し、エネルギーとして利用し運動するまでの間で
基準となる数値がかわります。
まとめ
ダイエット記事などで脂質を減らしましょう!とか、糖質制限しましょう!とか
目を引くような見出しが目立ちますが
糖質も脂質も悪いものではなく生命維持活動にとても重要な栄養素になります。
もちろん、過剰に摂取することは内臓疲労や肥満につながるリスクも含みますが
過剰に摂取を避けることも同じく生命維持を危険にさらす行為になると思います。
糖質も脂質もたんぱく質もただしく付き合い、摂取していくことが必要ですよね。
今回は3大栄養素の役割や特徴について中心にまとめました。
繰り返しますが、生命維持活動に必要な栄養素です。
くれぐれも過剰なことをして不健康にならないように
正しく付き合っていきましょう!
この記事があなたの健康の一助になれば幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました!