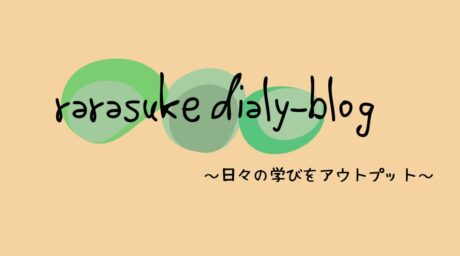今回は胎児期~青年期にかけての脳の成熟と発達についてまとめます。
脳の正常な成熟や発達は子どもの発達にも深く関わります。
また、発達障害などがある場合は青年期以降に加齢にともなう
脳機能の衰退も起こりやすいと言われています。
一緒に理解を深めていきましょう!
この記事を読んで分かること
- 胎児期~青年期の脳の正常な成熟・発達段階
- 胎児期~青年期の脳の成熟・発達の特徴
- 大脳では神経細胞がどのように変化するか
- 大脳のように高次脳機能は環境や働きかけで変化する可能性が高い
胎児期~青年期の脳の成熟・発達の特徴

・胎児期
受精卵から胚葉が分化していき神経細胞をどんどんと増やす時期です。
この神経細胞の増殖はおよそ妊娠9ヶ月ごろに停止すると言われています。
・胎児期~乳幼児期
神経細胞が移動し、シナプス形成とその増加が進行する。
神経細胞同士のネットワークがたくさん作られる期間。
これらのシナプスの形成は妊娠2ヶ月ごろから開始され
生後8~12か月ごろに最大になると言われています。
・乳幼児期~児童期
シナプスの調整が進み、脳機能が成熟していく時期。
3歳ごろには大脳機能が一応の完成をむかえる。

・青年期
増殖したシナプスがせん定され灰白質の減少、白質の増加がみられる。
不要なシナプスを減らすため、大脳の神経細胞の多く分布する灰白質が減少する。
一方で、神経細胞の軸索が伸びることで神経細胞同士の伝達が効率化される。
また、軸索が伸びることで、大脳の軸索の多く分布する白質が増加する。
脳の成熟の特徴
脳の成熟にともない神経細胞の軸索が髄消化される。
神経線維が髄消化すると、神経線維を伝わる電気信号がより早く伝わるようになります。
そのため、シナプス同士の伝導・伝達が効率よく行われるようになります。
また、大脳では「一次野⇒二次野⇒三次(連合)野」の順番で成熟するとされています。
一次野は運動や感覚といった基礎的な機能を司る領域のため比較的早い時期から成熟します。
一方、言語や認知を司る二次野やより高次の脳機能を制御する三次(連合)野は
機能の発達が一次野よりもゆっくりと発達するとされています。
神経発達障害では、神経系の発生や発達の段階で問題が生じ
その領域の発達や成熟が遅れることでみられる障害です。
この成熟の遅れた領域で制御される機能は加齢とともに機能も低下しやすいと言われています。

高次脳機能の発達は環境や働きかけによって変化する可能性が高いことから
小児リハビリテーションが重要な関わりとなります。
また、発達障害の既往を持つ方が高齢化したときに
地域や医療機関などでの関わり方も適切に行う必要があります。
高次脳機能障害に対して、適切に関わることで機能改善が見込める一方で
不適切な関わりでは発達がゆがんだり、機能改善が見込めない事態も想定されるとも言えます。
リハビリテーションのみではなく、家族や地域社会が連携して支援できる体制を
構築することが理想的とされています。
まとめ
この記事のまとめ
- 胎児期2か月~9ヶ月ごろで神経細胞が増殖
- 妊娠2ヶ月~生後8か月以降にシナプス形成と増加が進む
- 3歳ごろにかけて大脳の機能は一応の完成をむかえる
- 青年期にかけて脳機能の成熟とともにシナプスがせん定され効率化が図られる
- 基礎的な脳機能の発達は早く、高次脳機能は発達が遅い
- 成熟の遅れた脳機能は加齢で機能低下が起きやすい
- 高次脳機能の発達や改善には適切な対応が重要となる
適切な対応が重要とされますが
その対応策は個人の能力や機能によって変わります。
その人に合った方法があるため一概に「これだけやっとけば正解!」みたいな
答えがありません。
どのように関わるか、リハビリスタッフとしては
勉強をかさねて学び続ける必要がありますね。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございます!
気になる記事があれば他のページにもアクセスしてみてください。