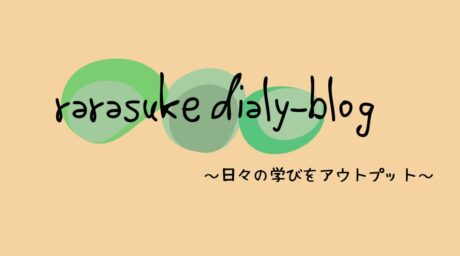理学療法に役立つ知識シリーズ
今回は筋肥大と筋力強化をテーマに勉強したことをアウトプットします。
普段のリハビリ業務でも取り入れることの多い筋力トレーニングですが
筋肥大を狙ったものと筋力強化を狙ったものでは目的や方法が異なります。
この記事でわかることは筋肥大と筋力強化の違いと
効率よく筋力強化または筋肥大を実現するための理論についてです。
理学療法士にも、筋トレ愛好家の皆さんにも分かりやすく解説していきますので
ぜひ、最後まで読んでみてください!
筋力強化と筋肥大の違い

安定の初手テーマ回収になります
「そもそも、筋力強化も筋肥大も一緒じゃないの?」という声が聞こえてきそうです
それに対しての答えは「半分正解で半分不正解」です
その理由について説明していきますね
まず、「半分正解」の部分からです
筋力強化も筋肥大も筋力増強運動を行った結果として起こる身体反応です
その点でいうと筋力強化も筋肥大も一緒とすることは正解といえます
では、なぜ「半分不正解」なのか説明するとき
キーワードになるのが「何が増強するのか」と「増強するタイミング」の2点になります
まず、何が増強するのかという点です
筋力増強運動を行うことで、初期に増えるものは「運動単位」や「中枢神経系の働き」です
もう少し噛み砕いて説明します
- 運動単位:その運動に参加する筋線維の数
- 中枢神経系の働き:複数化した運動単位の同期化
例えば、最初は1kgのダンベルを持つのもやっとな状態だとします。1kgのダンベルを持ち上げる練習を繰り返していると、その運動に参加する筋線維が増えていき、また、参加する筋線維の増えた上腕二頭筋を円滑に動かすために中枢神経系の指令も促されます。その結果、1kgよりも重いダンベルが持てるようになります
つまり、筋力増強運動の初期には筋肉の発揮できる出力が向上します

そして、次第に扱う負荷が増えて筋線維が破壊されます
その破壊された筋線維が修復される過程で筋線維が太くなり、筋断面積が増大します
つまり、筋肥大が起こるわけです
さて、増強するタイミングについても、先になんとなく説明しちゃいましたが
『筋出力の向上⇒筋肥大』のタイミングで起こります
具体的な期間については諸説ありますが、筋出力の向上は約1週間程度、視覚的に分かる筋肥大は2~3ヶ月程度かかると言われています
思ったより長くなってしまったので、この項目のまとめです
Q.筋力強化も筋肥大も一緒じゃないの?に対する回答は
- 筋力強化という概念の中の1つに『筋肥大』があるので半分正解
- 筋力強化という大きなくくりの中で『筋出力の向上』という過程を経て起こる『筋肥大』という現象であり、筋力強化≒筋肥大のため半分不正解
くどくど語りましたが、要するに筋量を増やしたり、筋肥大させるには時間がかかるということが分かっていただければ大丈夫です
筋力強化の3原理5原則
次に「どうやったら筋力強化できるのさ?」に答えていきます
結論は「3つの原理、5つの原則を知る」ことになります
簡単に紹介していきますね
筋力強化の3原理
- 過負荷の原理:日常生活以上の負荷を加えること
- 可逆性の原理:高めた体力・筋力もトレーニングをやめると元のレベルに戻ること
- 特異性の原理:目的によってトレーニングの方法が変わること
筋力強化の5原則
- 漸進性の原則:徐々に負荷を高めていくこと
- 全面性の原則:1部分だけでなく全身的に鍛えることでトレーニング効果が高まること
- 意識性の原則:トレーニングの意味や鍛錬する部位を意識することでトレーニング効果が高まること
- 個別性の原則:自分の性別、年齢、体格、能力に合った方法でトレーニングすること
- 反復性の原則:トレーニングを継続することで効果が高まること
これらの原理、原則を理解して、意識してトレーニングメニューを組んだり実践したりすることで効率的な筋力増強が望めます。また、自分にあった負荷量やフォーム、方法でトレーニングを行うため怪我の予防にもつながります
まとめ
筋力強化は「運動単位の増加」と「中枢神経系の働きの促進」
筋肥大は運動により破壊された筋線維が回復することで起こる、筋断面積の増大
効率よい筋力トレーニングを考えるうえでのポイントは「3つの原理と5つの原則」を活用すること
その他にも栄養や睡眠など様々な要素が影響するんですが
それについてはまた次回!
それではご閲覧ありがとうございました!