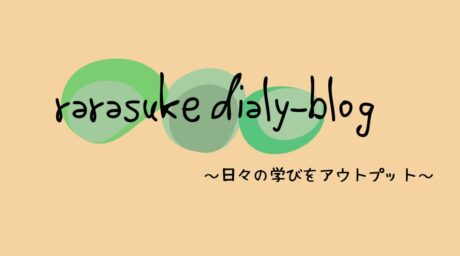今回は歩行時のエネルギー消費について解説します。
ダイエットや運動習慣の指導のなかで必ず触れるカロリー収支の話題です。
有酸素運動をして消費カロリーを増やしましょう!とは言われるけれど
実際にどのくらい消費しているか分からない...
そんな疑問にお答えします!
最後に計算式も紹介しているので
ダイエットや生活習慣の改善に頑張っている方は
ぜひ最後まで読んでくださいね!
それでは一緒に理解を深めていきましょう!

この記事で分かること
- エネルギー代謝の基礎知識
- 歩行の時のエネルギー消費に関わる要素
- 歩行時のエネルギー消費量の計算式
エネルギー代謝の基礎知識
歩行運動(有酸素運動)をしたときの消費エネルギーを知ることも大切ですが
前提として、エネルギー代謝の生理学を知っていることでより理解が深まります。
身体活動におけるエネルギー代謝で扱われるものは主に化学的エネルギーです。
- アデノシン三リン酸(ATP)
- クレアチンリン酸(CP)
- グリコーゲン
これらの分解過程で発生するエネルギーを用いて人間は生命活動をしています。
しかし、これらのエネルギーは限られたものであり、短時間の運動で多くが消費されてしまいます。
そのため、必要なエネルギーの大部分は食事によって摂り込まれた栄養素と
呼吸によって取り込まれた酸素が化学反応をおこすときに発生するエネルギーを使っています。
平均的な食事をおこなっている場合、酸素1L当たり約4.83kcalのエネルギーが発生するとされています。
そのため、運動時のエネルギー消費を測定するときは酸素消費量を用いて測定される場合が多いです。
心疾患患者様の運動耐容能評価のためのトレッドミル歩行やCPXなども酸素消費量を測定して
運動耐容能を評価されていますね。
この酸素消費量から、基礎代謝(安静状態で生命維持に必要な最小限エネルギー量)や
運動代謝量(運動時のエネルギー消費量)も測定されています。
基礎代謝と運動代謝の相対的比を求めると
安静臥位と比べて、歩行時ではおよそ4倍ものエネルギーが消費されていると言われています。
個人差はあるものの、体重70㎏の男性の1時間当たりのエネルギー消費は
睡眠時65kcal 安静臥位77kcal 歩行(4.2㎞/h)200kcal 走行(8.5km/h)570kcal
階段昇降(1時間)1,100kcal と言われています。
このエネルギー消費の計算には体重が関わります。
同じ歩行速度、同じ歩行距離で計算したとき、体重が重い人の方がエネルギー消費は大きくなります。
その理由について計算式を含め解説します。
歩行運動のエネルギー消費の計算方法
歩行時のエネルギー消費に関わる要素は以下のとおりです
- E:エネルギー消費(kcal/min)
- W:体重(kg)
- V:歩行速度(miles/h) 1mile=約1.6km
これらを用いた計算式がこちらです
E=W(0.03+0.0035V²)

例えば、体重70㎏の人が時速4.2㎞(約2miles)で1時間歩いたときのエネルギー消費は
0.0035 × 2²=0.014
70 ×(0.03+0.014)=3.08(kcal/min)
3.08×60=184.8kcal となります。
体重45㎏の人が同じ条件で1時間歩いたときのエネルギー消費はどうでしょうか
40 × (0.03+0.014)=1.76(kcal/min)
1.76 × 60=105.6 kcal となります。
つまり、同じ条件で同じ時間・距離を歩いたとき
体重が重い人の方がエネルギー消費が大きいということになりますね。
じゃあ、太ってるほうが痩せやすいのか!?といわれると
筋肉量や身体活動量によって基礎代謝が変化するので
個人差がありますよ、という答えになってしまいます。
このことからも、ダイエットにおける食事と運動の重要性がみえてきますね。
まとめ
今回は歩行の時のエネルギー消費についてまとめてみました。
いま、自分の行っている有酸素運動が概ねどれくらいのカロリー消費してくれているかの目安になるかと思います。
また、リハビリテーションの場面でも低栄養状態の方を対象に運動を実施するとき
摂取カロリー以上に運動をしてもかえって悪影響になってしまう可能性があります。
そのようなときの運動処方の目安やヒントになれば幸いです。
計算間違っていたらコメントで教えてください。
最後まで読んでいただきありがとうございました!