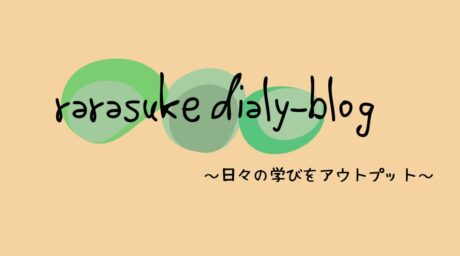この記事では胎児期~幼児期(~7歳頃まで)の運動発達の特徴をまとめたものです。
ボク自身も小児リハビリテーションを任されるようになり日々勉強中です。
一緒に理解を深めていきましょう。
この記事を読んで分かること
・胎児期
・乳児期(出生~2歳ごろ)
・幼児期(2~7歳ごろ)
・7歳以降
以上の時期ごとの運動発達の特徴について
胎児期の運動発達
胎児期の運動発達は自発的な運動と反射的な運動が形成される時期です。
人間では胎児期から自発的な運動が始まるとされています。
受胎後7週ほどで頭頚部から運動神経の支配がはじまり
体幹や四肢の筋群の神経支配まで完成します。
8週後から外部からの刺激による反射的な運動を示すようになります。
9週目になると呼吸や摂取、排泄など生命維持に関わる
自律機能として役立つ自発運動から開始されます。
その後、防御機能となる屈曲反射を示すようになり
さらに、把握動作や表情、姿勢保持、内臓機能などの発達がみられるようになります。
これらの発達は、延髄ー脊髄レベルの統合からはじまり
間脳や中脳、小脳などの統合が後を追って発達することで起こるとされています。
中枢神経系の成熟は脊髄から始まり、脳幹の上位中枢へ向かって進行します。
もっと噛み砕いて表現すると
脳みそから遠い方へとだんだんと神経系が成熟する。
それに伴って、反射運動から内臓機能まで成熟・発達が進むということです。
乳幼児期の運動発達(出生~2歳ごろ)

乳幼児期の運動発達は自発運動や反射運動から随意的な運動を獲得する時期です。
出生~3ヶ月頃までは胎児期と同様に自発運動と反射運動が主に行われます。
この時期の運動はジェネラルムーブメントとも呼ばれています。
これは新生児の大脳皮質からの神経ニューロンが細いことや、シナプスが少ないこと、伝導速度が遅いことなど中枢神経~末梢神経組織の発達が未熟なことが理由とされています。
生後3ヶ月~2歳頃にかけて、中枢神経の発達にともない随意運動がみられるようになります。
つまり、思い通り体を動かす能力を身に着けていく時期ということです。
この運動機能の成熟は、頭部 ⇒ 体幹 ⇒ 四肢へと波及していきます。
同時に、手で物を掴むことや指を動かすことなどの巧緻動作能力も徐々に身についていきます。
乳幼児期の運動発達は、姿勢・移動能力と手の把握・操作能力が獲得される時期と言われています。
この時期の発達について、いろいろな運動能力の獲得によって
子どもの環境への接触を促進し学習機会を増やすことに繋がることが重要視されています。
一方、随意運動の獲得が進むにつれて、原始的な反射運動は抑制されていきます。
これは、脊髄レベルでの反射的な運動から
大脳皮質や脳幹レベルでの制御された運動へと運動能力・技能が成熟するためと言われています。
これらの姿勢制御や移動能力、手の把握・操作能力の発達にともない
さまざまな運動の基礎となるだけでなく
食事や着替えなどの基本的な日常生活動作の自立が形成されていくとされています。
加えて、乳幼児期の発達段階を評価する指標として日本版デンバー式発達スクリーニング検査が有名です。
これは、運動発達だけでなく社会的行動を含めて評価する指標です。
しかし、乳幼児期の運動能力の発達や原始反射の消失は個人差があり、総合的に注意深く観察する必要があります。
幼児期の運動発達(2~7歳ごろ)

2~7歳ごろの運動発達は乳幼児期の初歩的な運動を基盤にして
基礎的運動パターンの量的獲得と質的変容の過程が特徴の時期です。
つまり、基礎的な姿勢制御や移動能力、操作能力が確立されていく時期です。
例えば、歩く、走る、回る、投げる、跳ぶなど、より複雑な身体操作を覚えていく時期ということです。
その獲得される運動レパートリーは成人と同程度の80種類以上にも及ぶとされます。
80種類以上の量的な運動パターンの獲得と
その運動パターンの精度が高まる質的な変化し、上達いく素晴らしい時期ですね。
学童期以降の運動発達(7歳~)

この時期の特徴は、基礎的な運動パターンがより洗練され専門的な運動へと分化・特殊化されていくことです。
日常生活やスポーツ場面などのさまざまな場面に応じて
より効率的な運動パータンを習得していくということになります。
この変化には神経系を含む身体の発育発達が大きく関与するとされています。
とくに、学童期は神経系の発達が顕著であり
その神経系の急速な発達にともない、運動コントロール能力も向上すると言われています。
また、思春期以降青年期をむかえると
身体的な成長にともにない、筋力や持久力など
狭義での体力も向上するため、より複雑で俊敏な運動が習得しやすくなるとされています。
まとめ
胎児期の発達は脊髄レベルでの生命維持のための呼吸や防御反射など脊髄レベルでの自律的な自発運動や反射運動が獲得される。
乳幼児期は自発運動や反射運動から徐々に随意的な運動に切り替わり、初歩的な運動の獲得(例えば、座る、立つ、歩く)がされる。
幼児期は初歩的な運動から、より多くの運動パターンを獲得し、その運動パターンの洗練が行われる。
学童期以降では、神経系の成熟や身体的な成長にともない、より複雑で俊敏な運動の習得がしやすくなる。
牛や鹿などの動物は天敵から身を守るため、生まれてすぐに立ち上がり、歩きだすのは有名な話です。
人間はコミュニティの中で、親が子を守り、安心と安全の中で成長するため、野生と比べると歩きだすまでに1年ほどかかってしまいます。
(個人的には、2足歩行に加えて、大脳が大きく進化したので、頭を支えて活動できるようになるための時間がかかるのも1つの要因だと思いますが...)
ですが、わずか3年あまりで成人と同程度の運動パターンを獲得できることに
勉強していて驚きました。
この記事を読んでくださった方にも、共感していただけたら幸いです。
小児リハビリの場面では
正常発達と比べて対象者様にはどんなアプローチが必要か
という視点が必要とされています。
より深く理解して、目の前の方の生活がよりよく変化するように
援助できるように勉強を続けていきます!
最後まで読んでいただきありがとうございました!